

地域のみなさまへ
保健医療交流事業 (講演会) レポート
●健康と睡眠 〜実はとても奥深い睡眠の世界〜
磐梯町・令和6年7月31日(水)
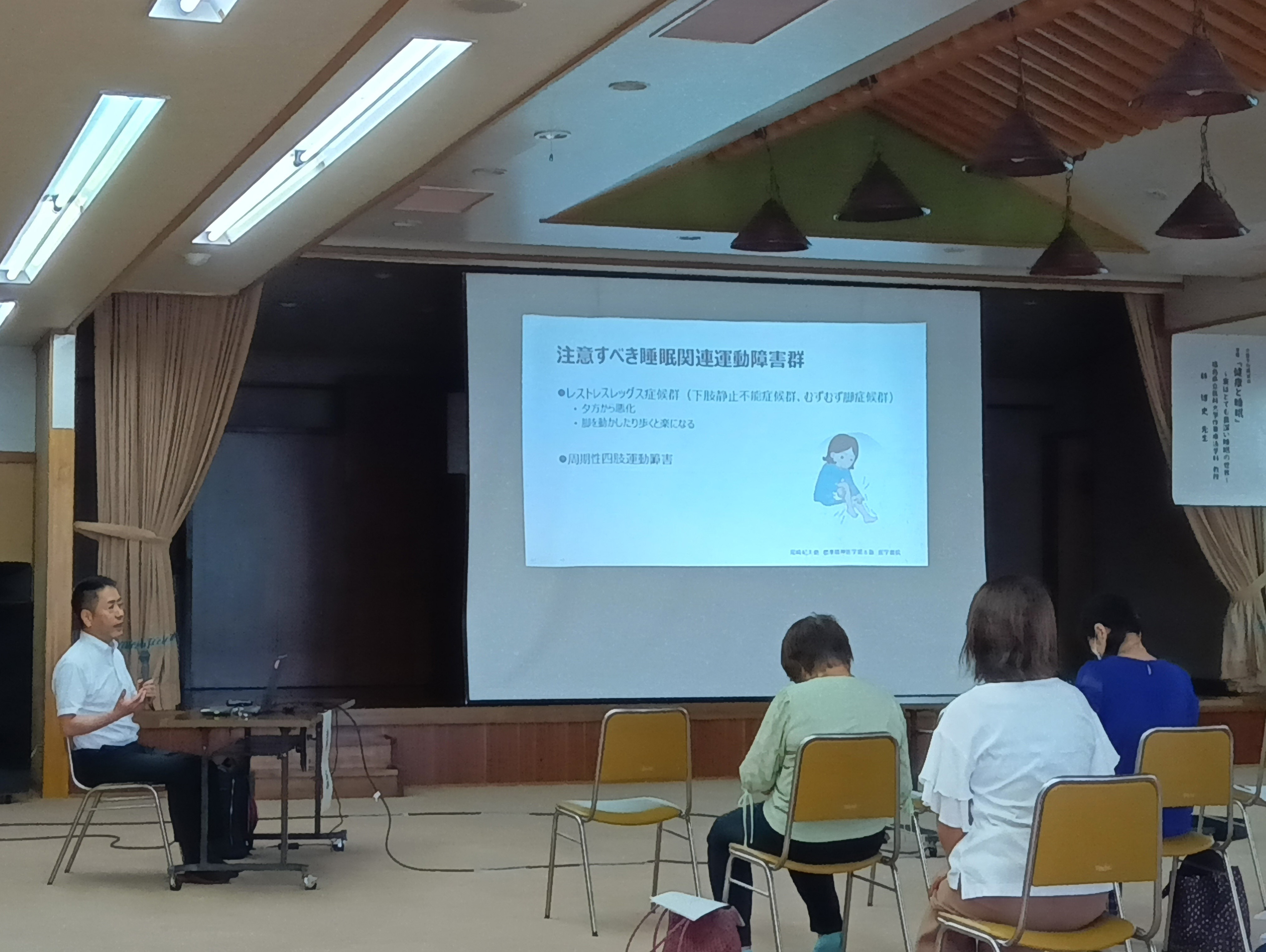

講演会は令和6年7月31日10時より磐梯町中央公民館講堂を会場に開催された。講師は保健科学部作業療法学科 林 博史教授が務められた。講演は「健康と睡眠 〜実はとても奥深い睡眠の世界〜」をテーマに行われた。
【講演内容】
※最初に睡眠に関する○×クイズを実施。講演を聞いてもらえば、全問正解できるとのこと。
〇加齢による睡眠の変化
・1日の平均睡眠時間の表を見ると、男女とも5時間未満の方が10%程度、逆に9時間以上の方も数%いる。適切な睡眠時間は人によって違うので、一概に何時間がよいとは言えない。大事なのは起きた後に疲れが取れた、すっきりしたという状態になること。
・睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠の2種類の睡眠があり、レム睡眠は夢を見ていることが多い、ノンレム睡眠は夢はほとんど見ないなどそれぞれ特徴がある。
・年代ごとの睡眠時間を見ると、年代が上がるにしたがって時間が短くなっている。また年代ごとの入床・起床時間を見ると、70代、80代は床にはいる時間は早くなっている。こうしたことから、70代、80代の高齢者は睡眠時間そのものは短いが、寝床にいる時間が長いということになる。
・床上時間・睡眠休養感と死亡リスクには床上時間が8時間以上と長く、睡眠休養感がないと死亡リスクが高まるというデータがある。
・良い睡眠を得るのに、必要なことは、適切な睡眠時間をとることと睡眠で休養がとれているという感覚(睡眠休養感)を得られる睡眠をとること。
〇不眠と高齢者に多い睡眠障害
・不眠に悩む高齢者は多く、特に80歳以上の高齢女性であれば、約40%が不眠を訴えている。
・睡眠時間が5時間未満と短くても、8時間以上と長くても認知症のリスクは上がる。
・不眠の原因はストレスや体や心の病気など様々あるが、その不眠が原因で日常生活に支障をきたすようになると不眠症という病気になる。
・不眠症の他に睡眠障害として注意すべきは睡眠関連呼吸障害群と言われているもの。これは大きないびきをかくのが特徴で睡眠の質の著しい低下や日中の眠気が発生する。そのほかにもレム睡眠行動障害、悪夢を見たり、手足をバタバタさせるなどの症状、むずむず足症候群と言われているものがある。こうした症状があれば専門医へ相談してほしい。
〇良い睡眠で健康に過ごすために
・最初に述べたように、良い睡眠に必要なものは、適切な睡眠時間と睡眠で休養が取れているという感覚(睡眠休養感)
・そのためには日中できるだけ日光を浴びる、寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まずできるだけ暗くする、といった環境づくりのほか、適度な運動習慣を身に着け、規則正しい生活習慣を維持するなどが必要。特に高齢者では、無理のない範囲で行う適度な運動を行うことで睡眠が改善する。
(この後、福島県作業療法士会で推奨している「花まる体操」を全員で実施)
・嗜好品としてコーヒーやたばこ、酒などについてもカフェインの取りすぎを抑えること、晩酌での深酒や喫煙などは睡眠の質を悪化させる可能性があるので控えた方がよい。
・先ほど話したように長時間寝床にいることで死亡リスクが高くなるので、実際に寝床にいる時間は実際に眠っている時間のプラス30分程度に抑えて、8時間以上にならないようにすると良い。
・睡眠休養感を高まらない場合は、カフェインのやニコチンの摂取の見直しや塩分の過剰摂取を控える(夜間頻尿の原因となるため)、50歳代から徐々に増加する睡眠時無呼吸やむずむず脚症候群などの症状があれば医師に相談するなどしてほしい。
※最後に〇×クイズの答え合わせと質問を受け付け講演を終了した。
※最初に睡眠に関する○×クイズを実施。講演を聞いてもらえば、全問正解できるとのこと。
〇加齢による睡眠の変化
・1日の平均睡眠時間の表を見ると、男女とも5時間未満の方が10%程度、逆に9時間以上の方も数%いる。適切な睡眠時間は人によって違うので、一概に何時間がよいとは言えない。大事なのは起きた後に疲れが取れた、すっきりしたという状態になること。
・睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠の2種類の睡眠があり、レム睡眠は夢を見ていることが多い、ノンレム睡眠は夢はほとんど見ないなどそれぞれ特徴がある。
・年代ごとの睡眠時間を見ると、年代が上がるにしたがって時間が短くなっている。また年代ごとの入床・起床時間を見ると、70代、80代は床にはいる時間は早くなっている。こうしたことから、70代、80代の高齢者は睡眠時間そのものは短いが、寝床にいる時間が長いということになる。
・床上時間・睡眠休養感と死亡リスクには床上時間が8時間以上と長く、睡眠休養感がないと死亡リスクが高まるというデータがある。
・良い睡眠を得るのに、必要なことは、適切な睡眠時間をとることと睡眠で休養がとれているという感覚(睡眠休養感)を得られる睡眠をとること。
〇不眠と高齢者に多い睡眠障害
・不眠に悩む高齢者は多く、特に80歳以上の高齢女性であれば、約40%が不眠を訴えている。
・睡眠時間が5時間未満と短くても、8時間以上と長くても認知症のリスクは上がる。
・不眠の原因はストレスや体や心の病気など様々あるが、その不眠が原因で日常生活に支障をきたすようになると不眠症という病気になる。
・不眠症の他に睡眠障害として注意すべきは睡眠関連呼吸障害群と言われているもの。これは大きないびきをかくのが特徴で睡眠の質の著しい低下や日中の眠気が発生する。そのほかにもレム睡眠行動障害、悪夢を見たり、手足をバタバタさせるなどの症状、むずむず足症候群と言われているものがある。こうした症状があれば専門医へ相談してほしい。
〇良い睡眠で健康に過ごすために
・最初に述べたように、良い睡眠に必要なものは、適切な睡眠時間と睡眠で休養が取れているという感覚(睡眠休養感)
・そのためには日中できるだけ日光を浴びる、寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まずできるだけ暗くする、といった環境づくりのほか、適度な運動習慣を身に着け、規則正しい生活習慣を維持するなどが必要。特に高齢者では、無理のない範囲で行う適度な運動を行うことで睡眠が改善する。
(この後、福島県作業療法士会で推奨している「花まる体操」を全員で実施)
・嗜好品としてコーヒーやたばこ、酒などについてもカフェインの取りすぎを抑えること、晩酌での深酒や喫煙などは睡眠の質を悪化させる可能性があるので控えた方がよい。
・先ほど話したように長時間寝床にいることで死亡リスクが高くなるので、実際に寝床にいる時間は実際に眠っている時間のプラス30分程度に抑えて、8時間以上にならないようにすると良い。
・睡眠休養感を高まらない場合は、カフェインのやニコチンの摂取の見直しや塩分の過剰摂取を控える(夜間頻尿の原因となるため)、50歳代から徐々に増加する睡眠時無呼吸やむずむず脚症候群などの症状があれば医師に相談するなどしてほしい。
※最後に〇×クイズの答え合わせと質問を受け付け講演を終了した。
お問い合わせ: 医療研究推進課 研究推進係
電話 024-547-1794 / FAX 024-581-5163
Eメール
※ スパムメール防止のため一部全角表記しています
